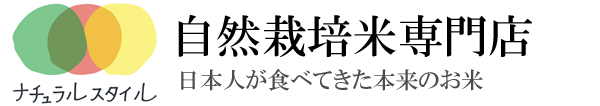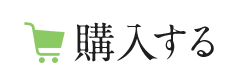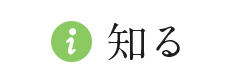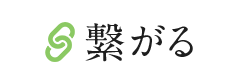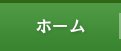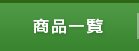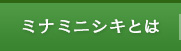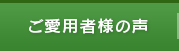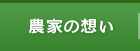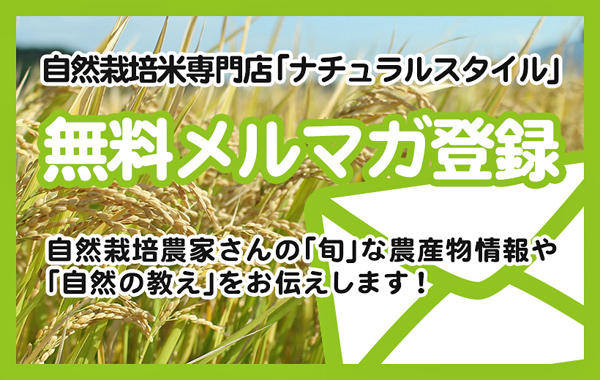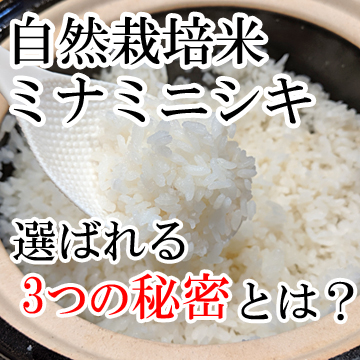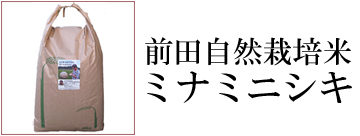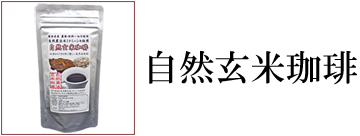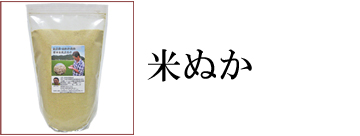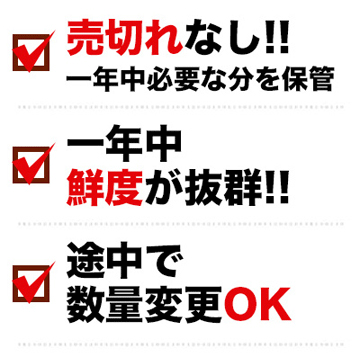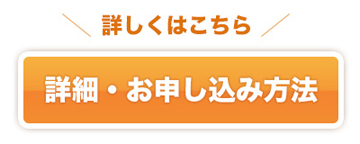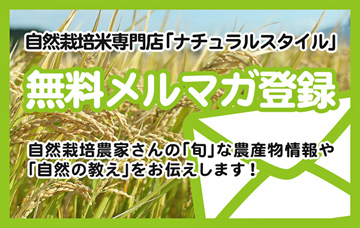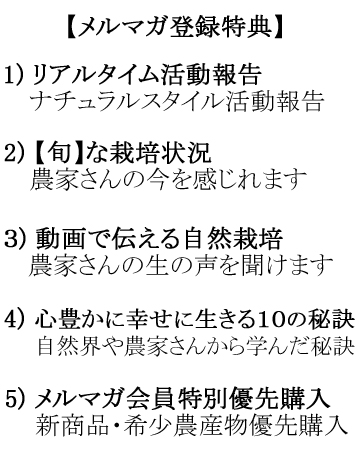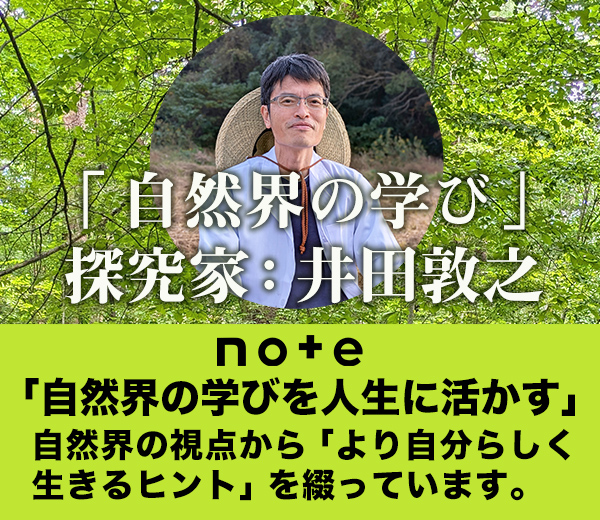こんにちは!自然栽培米専門店ナチュラルスタイルの井田敦之です!
熊本県玉名市の前田英之さんのミナミニシキの出来は年々良くなってきています。
その理由は、年々改良を重ねてきているためです。そして、気が付けば、周りの農家さんとは異なった方法で育てています。
今回は、前田さんの自然栽培米ミナミニシキの播種方法や種籾の違いに関してお伝えします。
苗作りは米農家にとって非常に重要な作業です。
「苗半作(なえはんさく)」という言葉もあるように、苗の出来はその年の収穫量に大きく影響する言われているからです。
熊本県玉名市で自然栽培ミナミニシキを作る前田さんも「苗作りには、米作り全体の60%の精神力を注ぐ重要な作業」と言うほど、苗作りにはこだわりを持っています。
今回は、前田さんの他とは異なる播種方法や種籾の違いについて紹介します。
<目次>
一般的な播種時の種籾

※上写真:催芽処理後の種籾(種籾から芽がちょこっと出ています)
お米作りにおいて播種作業とは、育苗箱に種籾を蒔く作業で一般的に4月~5月下旬頃に行われます。
播種作業の準備段階として、ほとんどの米農家さんが催芽(芽出し)処理を行います。これは種籾を一定期間浸水させ、上写真のように芽を出させる作業です。
催芽処理により播種後の苗の生育が均一になり、生育が揃うことによりその後の管理がしやすくなるのです。
世の中の99%以上の米農家さんが催芽(芽出し)をしているのではないでしょうか。
前田さんこだわりの播種時の種籾

前田さんの播種前の種籾を見ると、催芽(芽出し)はしておりません。そのままの種籾なんですね。
前田さんは、苗が健やかに育つようこれまで播種作業において改良を重ねてきました。
その改良の一つとして、約10年前から取り組んでいるのが、催芽(芽出し)をせず種籾を直接育苗箱に蒔くことです。
そのため前田さんの播種作業では、一つの育苗箱に通常の倍の種籾が投入されます。
播種する種籾が多いと育った苗は密集状態になり、成長具合が揃いません。それなのに前田さんはなぜ、密集状態にして、かつ芽出しをしないのでしょうか。
強い苗を育てるため

前田さんは苗作りにおいて「苗床でいかに強い苗を育てるか」という点を重要視しています。
芽出しを事前にして揃えないことで、力強く発芽する苗が残ります。また程よい密集状態にすることで苗どうしが競争をすると言います。
生育が揃うように人間が調整するのは不自然なことだと考えているのですね。
また、種籾が発芽する環境も自然の状態に任せたいと考えています。
「芽出しの水は田んぼの水で、田んぼの菌の中で発芽させる。微生物たちの働きで種籾が守られ、強くなる」と。
この発想を持っている米農家さんは少ないです。
農作業の省力化を図るため
通常芽出しには、約7日~10日間の日数を要します。
芽出しをしないということは、それだけ作業日数がかからないということ。前田さんは、次の世代の米農家が行う播種作業において、なるべく負担を減らしたいと思っています。そのために試行錯誤を繰り返し、今の方法に辿り着いています。
芽出しをしないことは、播種作業の省力化にもつながっているのです。
詳しくは下の動画をご覧ください!
なぜ催芽(芽出し)をせずに播種!
熊本県玉名市自然栽培米ミナミニシキを作る前田英之さんに特殊な播種方法伺いました。
前田さんの播種時のこだわりを感じて頂ければと思います。
まとめ:種籾の芽出しをしない理由とは!?
自然栽培とは、単に農薬や肥料を使用しないだけではないのです。
農薬や肥料を使用しないという制限がある中で、農家さんの栽培方法には個性が表れます。
今回は、自然栽培米ミナミニシキを育てる前田さんの播種作業を見させて頂きましたが、一番の特徴は、なんといっても強い苗作りのため催芽(芽出し)をしないこと。
一年に一回の苗作りなので失敗ができません。これまで催芽をしてきた人からすると、この催芽をしないというのは、実はすごい挑戦なのです。
前田さんは、催芽をしない事以外にも、「育苗土に無農薬・無肥料の山土を使用する」や「自家採種歴30年以上の種籾を使用する」などと積み重ねてきた歴史があります。
この積み重ねにより、厳しい環境下でも苗自身が順応して逞しく成長すると考えているんですね。
気候変動の激しい昨今ですが、力強いミナミニシキをお届けしていきたいと思います。